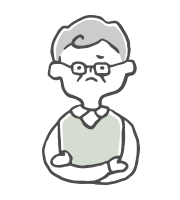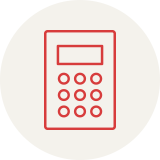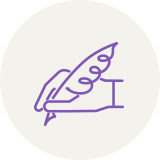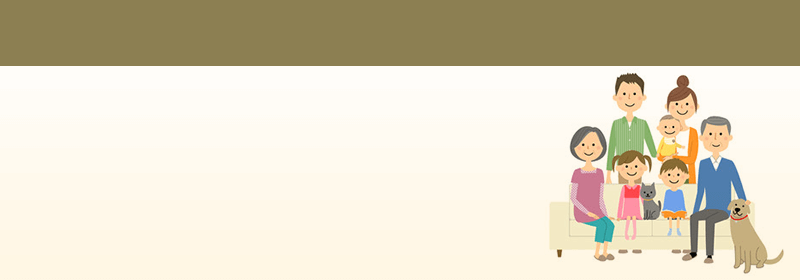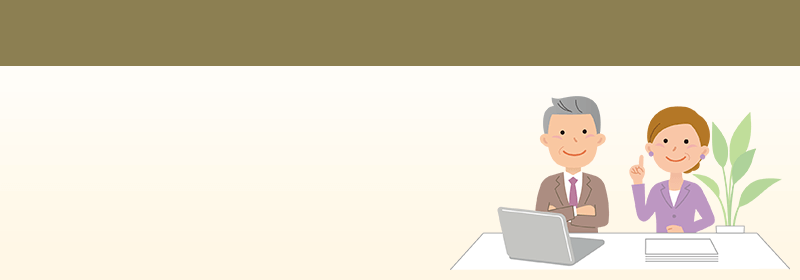【相続登記】死後(相続発生後)3年間、相続登記をしないで放置していたケース
相続登記を放置するとどうなる?義務化による罰則やデメリットを専門家が解説
「実家を相続したけど、手続きが面倒でそのままにしている…」
「相続登記はいつまでにやればいいの?」
このように、相続した不動産の登記手続き(名義変更)を先延ばしにしている方は少なくありません。しかし、2024年(令和6年)4月1日より相続登記が義務化され、相続登記を放置することのリスクはこれまで以上に大きくなりました。
正当な理由なく期限内に登記をしない場合、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。
ここでは、相続登記を放置した場合の具体的なデメリットや、義務化のポイント、そして実際に手続きが複雑になってしまった事例を交えながら、司法書士が分かりやすく解説します。
相続登記を放置する5つの大きなデメリット・リスク
過料の他にも、相続登記を放置することには様々なデメリットやリスクが伴います。時間が経てば経つほど、手続きは複雑になり、費用も高くなる傾向があります。
1不動産の売却や担保設定ができない
不動産を売却したり、ローンを組むために担保(抵当権)を設定したりするには、その不動産の所有者として登記されている必要があります。相続登記が完了していないと、自分名義の不動産ではないため、これらの法律行為が一切できません。いざ売却したいと思っても、すぐに手続きを進められないという事態に陥ります。
2相続人が増え、遺産分割協議が困難になる
相続登記をしない間に、当初の相続人(例えば兄弟)が亡くなってしまうと、その人の相続権はさらにその子供や配偶者へと引き継がれます(数次相続)。
最初は兄弟2人だけの話し合いで済んだはずが、甥や姪など、面識の薄い親戚も関係者となり、全員の同意(実印と印鑑証明書)が必要になります。時間と共に相続関係はネズミ算式に複雑化し、話し合いがまとまらず、手続きが非常に困難になるケースが後を絶ちません。
3他の相続人の債権者に持分を差し押さえられるリスク
遺産分割協議が終わっていても、相続登記をしていなければ、法定相続分に応じた持分が各相続人にあると見なされます。もし、他の相続人の誰かに借金があり、その債権者が不動産の持分を差し押さえた場合、全く無関係の第三者が共有者として登場する可能性があります。こうなると、不動産の利用や売却が極めて困難になります。
4認知症などによる判断能力の低下
相続人の誰かが認知症などにより判断能力が低下してしまうと、その人は遺産分割協議に参加できません。その場合、家庭裁判所で「成年後見人」を選任する必要があり、手続きには時間も費用もかかります。放置している間に、相続人の誰かが高齢になることで、このようなリスクも高まります。
5手続きの費用や時間が増大する
時間が経つと、相続人が増えるだけでなく、役所で取得するべき戸籍謄本などの書類も増え、収集が困難になります。住所を転々としている相続人がいれば、その所在調査も必要です。その結果、司法書士に依頼する際の費用も、相続発生直後に比べて高額になることが一般的です。
【事例】相続登記を3年間放置し、手続きが複雑になったケース
ご状況

相談者様は、3年前にご主人を亡くしました。ご自宅の相続登記が必要だと認識していましたが、ご主人には預貯金などの財産がほとんどなく、自宅くらいしか遺産がなかったため、手続きをせずに放置していました。
亡くなったご主人には前妻との間に数人のお子さんがおり、葬儀にも参列してくれました。しかし、その場で「相続登記に協力してください」とは切り出せず、時が過ぎてしまったとのことでした。
数年が経ち、ご自身の体調にも不安を感じ始めた相談者様は、「このままではいけない」と当事務所にご相談に来られましたが、その時点では前妻のお子さんたちの現在の住所が分からなくなっていました。
当事務所のご提案とサポート
当事務所でご依頼を受け、戸籍謄本等を取り寄せ、相続人調査を行ったところ、前妻のお子さんの一人が既に亡くなっていることが判明しました。
これにより、亡くなったお子さんのご家族(配偶者とお子さん)にも相続権が発生し、その方々にも手続きへの協力をお願いする必要が出てきました。つまり、当初は協力をお願いするはずだった相続人がさらに増えてしまったのです。
当事務所からお手紙を出し、事情を説明した結果、幸いにも皆様からご協力をいただくことができ、無事に相続登記を完了できました。しかし、もし相続発生後すぐに手続きをしていれば、直接面識のない方々にまでお願いする必要はなく、費用も時間も大幅に抑えられていました。
専門家からのポイント
今回のケースでは皆様にご協力いただけましたが、中には協力を拒否されたり、協力の見返りとして「ハンコ代」を要求されたりするトラブルも少なくありません。相続登記の放置は、百害あって一利なしです。少しでも早く専門家にご相談ください。
相続登記の義務化について(行政機関の情報)
所有者不明の土地が社会問題となる中、その発生を予防するため、不動産登記法が改正され、相続登記が義務化されました。以下に、法務省の情報を基にポイントをまとめます。
手続きの期限は「3年以内」
相続登記の申請義務は、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日」から3年以内と定められています。簡単に言えば、「不動産を相続したことを知った日から3年以内」に名義変更の手続きをしなければなりません。
違反した場合の罰則
正当な理由がないのに申請をしなかった場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
過去の相続も対象
義務化の施行日(2024年4月1日)より前に開始した相続についても、3年の猶予期間が設けられています。つまり、過去に相続した不動産でまだ登記をしていない場合も、2027年3月31日までに登記をする必要があります。
出典: 法務省:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
相続・遺言の無料相談を実施中!
相続手続きや相続登記、遺言書作成、成年後見など、相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が、ご家庭の状況を丁寧にお伺いし、最適な手続きをご提案させていただきます。まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤル:049-299-7960

料金のご案内
遺産整理業務(不動産・預貯金など全ての財産の手続きを代行)
司法書士が遺産管理人として相続人の皆様の窓口となり、あらゆる相続手続きを一括でお引き受けするサービスです。
「専門家に間に入って遺産分割協議を進めてほしい」「相続手続きを丸ごと代行してほしい」という方におすすめです。
| 相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 200万円以下 | 22万円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 27.5万円 |
| 500万円を超え5,000万円以下 | 価額の1.32% + 20.9万円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 価額の1.1% + 31.9万円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 価額の0.77% + 64.9万円 |
| 3億円以上 | 価額の0.44% + 163.9万円 |
※ 金融機関が2行以上の場合、1行につき3万円の追加費用となります。
※ 相続人が4名様以上の場合、1名様につき5,000円を加算させていただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条に基づき、司法書士が遺産管理人として遺産整理業務を行います。
坂戸・東松山・鶴ヶ島で無料相談受付中!
- 初回相談無料!
- LINEで
予約可能! - 相続の
専門家が対応! - 無料相談はこちら
主な相続手続きのメニュー
相続のご相談は当相談窓口にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧
坂戸・鶴ヶ島・東松山で
相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで