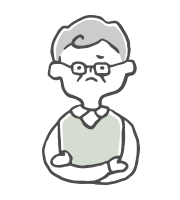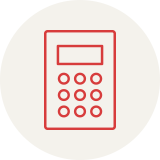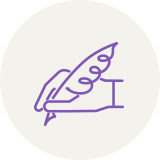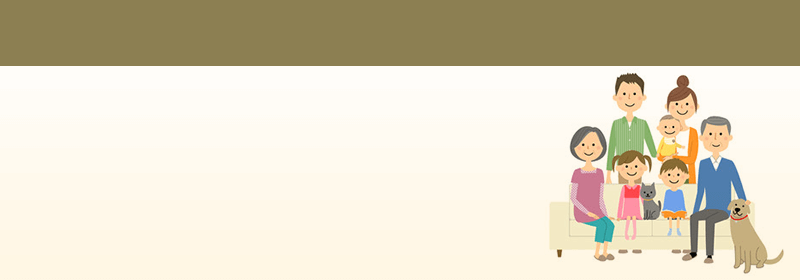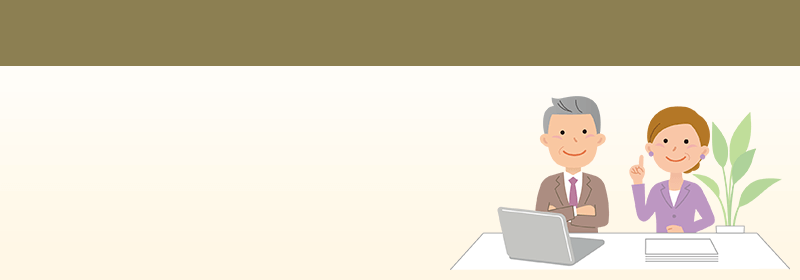遺産分割協議のQ&A
クリックした箇所に遷移します
- Q1)夫が亡くなりました。相続人は私(妻)と息子の2人です。息子はまだ16歳の未成年者です。このままの状態で遺産を分割することができるのでしょうか?
- Q2)夫が亡くなりました。現在私は妊娠中で、2人目の子がお腹の中にいます。お腹の中の子は相続権があるのでしょうか?また、胎児も相続人になるならば、遺産分割はどのようにしたらよいのでしょうか?
- Q3)相続人の中に音信不通で、所在不明の者がいます。このような場合は、その人を除外して遺産分割協議をしても良いのでしょうか?
- Q4)父が亡くなりました。遺産分割の話し合いをした後になって、父の子と名乗る人物が現れました。この場合、遺産分割協議はもう一度やり直さなければなりませんか?
- Q5)実印の登録をしていません。遺産分割協議書には認印を押しても大丈夫ですか?
- Q6)相続人のうちの1人が海外に住んでいます。実印の登録ができないのですが、どうすれば良いですか?
- Q7)遺産分割協議書は何通作成すれば良いでしょうか?相続人の人数分つくらなければいけませんか?
- Q8)「借金やローンは全て長男が相続する」という内容の遺産分割協議はできますか?
- Q9)母が亡くなり、遺産を子供2人で相続します。遺産分割については特に争いもなく、子供達2人の間では、すぐに遺産分割の合意ができました。遺産についての争いがない場合には、遺産分割協議書は作成しなくても大丈夫ですか?
- Q10)父が亡くなりました。父の書斎から遺言書が見つかりました。しかし、子供たち全員で話合った結果、遺言書とは違う内容で遺産を分割したい、ということになりました。このことに問題はないでしょうか?
- Q11)父の遺産(土地、現金)を、子供3人で、遺産分割協議書を作成して相続しました。後になって、別の銀行に預金(800万円)がある事が判明いたしました。遺産分割協議はやり直しになりますか?
- Q12)父が亡くなり、母と子供2人で遺産分割協議をしました。半年後に、父の遺言書が見つかりました。遺産分割協議の内容と遺言書の内容には、違うものです。この場合、既に遺産分割協議が終わっていますが、どのようにしたら良いでしょうか?
Q1)夫が亡くなりました。相続人は私(妻)と息子の2人です。息子はまだ16歳の未成年者です。このままの状態で遺産を分割することができるのでしょうか?
A1)このままの状態では遺産分割はできません。
まず、お子さんは未成年なので、自分自身で法律行為(契約や遺産分割協議など)をすることはできません。自分自身で契約等をしても、後で取り消されてしまうことがあります。
子が未成年の場合は、「親が法定代理人として、子の法律行為を行う」というのが原則です。
しかし、ご質問のケースでは、ご質問者(親)も相続人の一人です。このような場合には、親の利益とこの利益が相反する状態になってしまっています(「利益相反」と呼ばれます)。たとえば、親の相続する分を増やすと、子が相続する分が減ってしまうことになりますので、親と子で利益が相反する状態になってしまっています。
このような場合には、親は、子の法定代理人として遺産分割をすることは出来ないことになっています。遺産分割が公平に行われない可能性があるからです。
このようなケースでは、親権者であるあなた以外に、遺産分割協議を行うためだけの代理人(この場合、「特別代理人」と呼ばれます)を、選んでもらう必要があります(民法第826条)。
親権者であるあなたは、家庭裁判所に申し立てをして、子の特別代理人を選任してもらう必要があります。そのうえで、その特別代理人との間で、遺産分割の協議をする必要があります。
特別代理人の選任申立ては、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
申立に必要な書類は下記のとおりです。
・申立書
・申立人(親権者)、未成年者の戸籍謄本
・特別代理人候補者の戸籍謄本、住民票
・遺産分割協議書の文案、及びその資料(不動産登記事項証明書など)
・連絡用の郵便切手
※事案によっては、他に資料が必要になる場合があります
Q2)夫が亡くなりました。現在私は妊娠中で、2人目の子がお腹の中にいます。お腹の中の子は相続権があるのでしょうか?また、胎児も相続人になるならば、遺産分割はどのようにしたらよいのでしょうか?
A2)胎児の相続権について、民法にこのような規定があります。
【民法 第886条】
①胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
②前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
よって、お腹の中の子も、相続人としての権利があります。
では、どのように遺産分割をすれば良いでしょうか。
もし、胎児が生まれてくることを前提に、先に遺産分割協議をしてしまうと、「双子だった」、あるいは「流産してしまった」等の場合に、相続人の人数が変わってしまいます。
胎児がいる場合の遺産分割については、学者の先生の間でも意見が分かれています。①胎児が生まれるまでは遺産分割協議はできないという見解、②遺産分割協議はできるが、生まれてきた場合には、事後、金銭による支払をすればよいという見解、などがあります。
先に述べた理由から考えても、胎児が生まれるまでの間は、遺産分割をするのは待っていた方が無難だと考えられます。
Q3)相続人の中に音信不通で、所在不明の者がいます。このような場合は、その人を除外して遺産分割協議をしても良いのでしょうか?
A3)その人を除外して遺産分割協議をすることは出来ません。
相続人のうちの1人が行方不明・所在不明の場合には、そのままの状態で遺産分割協議をすることは出来ません
この場合、所在不明の人(以下、「不在者」と表現します)の財産・権利を守るために、不在者の財産管理人を選任してもらう必要があります。
具体的には、家庭裁判所に対して、不在者の財産管理人の選任を申立てることになります。そして、選ばれた財産管理人が、不在者の代わりに遺産分割協議に参加します。
なお、「電話番号が分からない」「連絡先が分からない」というような状況だけでは、この方法をとれません。「警察へ捜索願をしたのに、見つかっていない」「本人の住民票を取得して、その場所を訪問したが、別の人が住んでいた」などの事情がないと、不在者の財産管理人を選任することは出来ない可能性があります。
また、上記の方法の他に、「行方不明の状態が長く続いている」というような場合には、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをして、その人が死亡したものとして、遺産分割協議をする方法もあります。
Q4)父が亡くなりました。遺産分割の話し合いをした後になって、父の子と名乗る人物が現れました。この場合、遺産分割協議はもう一度やり直さなければなりませんか?
A4)戸籍謄本を取得して、その人物がお父様の子であることを確認する必要はありますが、子であることが確認された場合には、やはり遺産分割のなり直しが必要です。
相続人のうち、1人でも遺産分割協議に参加していない人がいる場合には、その遺産分割協議は有効とは言えません。やはり、全員そろった状態で遺産分割協議をし直す必要があります。
Q5)実印の登録をしていません。遺産分割協議書には認印を押しても大丈夫ですか?
A5)実印を押してください。認印を押しても、その後に財産の名義変更手続きができません。
財産の名義変更の際は、遺産分割協議書を銀行や法務局に提出することになります。その際に、実印が押されていないと、法務局や銀行で、手続きが止まってしまいます。
印鑑登録をしていない場合には、住所地の市区町村役場に行き、印鑑登録をしてください。
なお、印鑑登録の際には顔写真付きの身分証明書の提示が求められます。
Q6)相続人のうちの1人が海外に住んでいます。実印の登録ができないのですが、どうすれば良いですか?
A6)遺産分割協議書にサインをして、『署名証明書』(または拇印証明書)という書類を取得してもらいます。
海外在住の人がいる場合でも、まずは遺産分割の話し合いが必要です。話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。そして、相続人がサインする際に、相続人が住んでいる国にある日本大使館、日本領事館等で、『この署名は本人のものに間違いがない』という証明文書を作ってもらいます。
なお、相続人の方が在住している国によっては、その国の公証人の公証で足りる場合があります。
国によって手続きが違う場合があります。国によっては印鑑登録が可能な場合もあります。
海外に在住している方がいる場合には、手続きが複雑になりますので、専門家に相談することをお勧めします。
Q7)遺産分割協議書は何通作成すれば良いでしょうか?相続人の人数分つくらなければいけませんか?
A7)民法上、とくに決まりはありません。1通しか作らないケースもありますし、相続人の人数分作成する(各人が1通ずつ保管する)ケースもあります。
遺産の相続手続きをする際に、登記所や銀行に遺産分割協議書を持っていくことになります。
その際に、遺産分割協議書が1通しかないと、手続きが不便になると思われます。そこで、一般的には遺産分割協議書を3~4通ほど作っておくと、相続手続きの際に便利かと思います。
Q8)「借金やローンは全て長男が相続する」という内容の遺産分割協議はできますか?
A8)相続人の間でそのような遺産分割協議をすることは、可能です。ただし、そのことを債権者に主張できるわけではありません。
債権者は、法定相続分の割合で、各相続人に返済を求める権利を持っています。したがって、たとえ相続人間で「借金は全て長男が相続する」という合意をしたとしても、そのことは債権者に対抗することができません。
なぜなら、たとえば上の事例で、長男に借金の返済能力がなかった場合、「その人だけに借金を背負わせて、他の相続人が借金から逃れる」ということができてると、債権者を害する結論になってしまうからです。
特定の人のみが借金を承継することにしたい場合には、債権者の同意・承諾が必要になります。
したがって、上記の事例で、債権者が、「借金を全て長男が相続すること」に関して同意・承諾する場合には、長男だけが借金を承継することができます。
Q9)母が亡くなり、遺産を子供2人で相続します。遺産分割については特に争いもなく、子供達2人の間では、すぐに遺産分割の合意ができました。遺産についての争いがない場合には、遺産分割協議書は作成しなくても大丈夫ですか?
A9)遺産分割協議書は、法律で作成を義務付けられているものではありません。
しかし、口頭で合意しただけでは、数年後に「言った」「言わない」の争いになることも考えられます。このような紛争を防ぐために、遺産分割の内容は書面にして残したほうが良いでしょう。
また、各種の相続手続きにおいて、登記所や銀行窓口等で、遺産分割協議書の提出が要求される場合が多いです。
例えば遺産分割協議をして不動産を相続する場合には、登記所において遺産分割協議書の提出が求められます。
Q10)父が亡くなりました。父の書斎から遺言書が見つかりました。しかし、子供たち全員で話合った結果、遺言書とは違う内容で遺産を分割したい、ということになりました。このことに問題はないでしょうか?
A10)遺言があっても、相続人全員の同意があれば、遺言と異なる遺産分割協議は可能です。 ただし、遺言による遺贈があれば、受遺者の同意も必要です。
また、遺言書とは異なる内容で分割する場合でも、その遺言書が存在していることは、相続人の全員に知らせる必要があります。この通知を省略してしまうと、場合によっては「遺言書の隠匿」とみなされてしまう可能性があります。
遺言書がある場合には、専門家に一度ご相談することをお勧めします。
Q11)父の遺産(土地、現金)を、子供3人で、遺産分割協議書を作成して相続しました。後になって、別の銀行に預金(800万円)がある事が判明いたしました。遺産分割協議はやり直しになりますか?
A11)全てをやり直す必要はありません。
新たに預金が判明したことにより、その預金のみの分割協議をし直せば、遺産分割をすることができます。すでに行った遺産分割協議の全てをやり直す必要まではありません。
Q12)父が亡くなり、母と子供2人で遺産分割協議をしました。半年後に、父の遺言書が見つかりました。遺産分割協議の内容と遺言書の内容には、違うものです。この場合、既に遺産分割協議が終わっていますが、どのようにしたら良いでしょうか?
A12)遺言は、遺言者の最後の意思が表現された者です。遺言の内容は尊重されるべきものであり、優先されるものです。
遺産分割協議の終わった後に遺言が見つかった場合には、遺言に反する部分については、遺産分割協議が無効になります。
しかし、相続人や受遺者が遺言の内容を確認し、遺産分割をやり直さないことに同意すれば、既に行った分割協議の内容で、遺産を分割することになります。
この記事の執筆者

- 中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
-
保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号) 経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録
坂戸・東松山・鶴ヶ島で無料相談受付中!
- 初回相談無料!
- LINEで
予約可能! - 相続の
専門家が対応! - 無料相談はこちら
主な相続手続きのメニュー
相続のご相談は当相談窓口にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧
坂戸・鶴ヶ島・東松山で
相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで