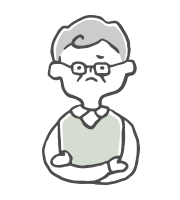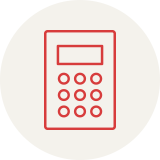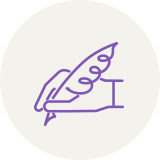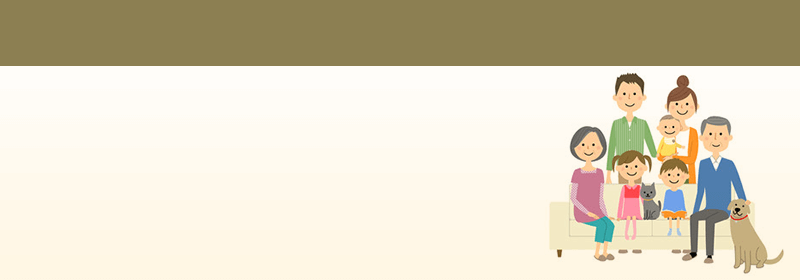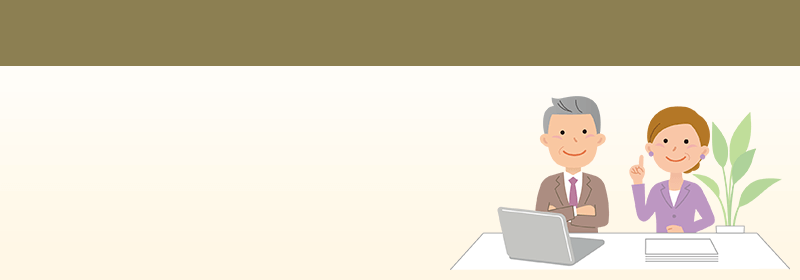相続登記義務化のポイント!放置すると罰則があります
相続登記が義務化される見込みです。
今回は、相続登記義務化の概要と法改正のポイントを司法書士が解説します。
クリックした箇所に遷移します
相続登記が義務化される背景

相続登記が義務化されることとなった背景には、「所有者不明の土地や不動産」や「所有者と連絡のつかない土地や不動産」が増えたことにあります。
所有者不明の土地や空き家の増加によって、景観が悪化し周辺の地価の下落や、公共事業や土地開発が進まないなどの問題が発生するのです。
空き家、荒地なら行政が勝手に整備や土地活用をしたらよいのでは?と思われるかもしれませんが、それは法的に認められません。
土地や不動産を処分や活用、売買をする場合、所有者の同意が必須だからです。
これまでは相続登記が義務化ではなかったため、放置される相続人がおられました。
結果、所有者の分からない土地や不動産が増え、土地の活用に悪影響を及ぼしたため相続登記が義務化されることとなりました。
日本の所有者不明の土地はどれくらいある?
法務省による不動産登記簿における相続登記がされていない土地調査の結果(平成29年法務省調査)、最後の登記から50年以上経過している土地の割合は大都市で約6.6%、中都市・中山間地域で約26.6%という結果がでています。
さらに、地籍調査における土地所有者等に関する調査(平成30年版土地白書114頁参照)によれば、不動産登記簿のみでは所有者の所在が確認できない「所有者不明の土地」は約20.1%です。
2016年時点では、九州本島の面積(約367万ヘクタール)を上回り、約410万ヘクタールに達しました。
このままでは北海道本島の土地面積(約780万ヘクタール)に匹敵する720万ヘクタールに到達する、という試算結果もあります。
相続登記義務化はいつから?

相続登記の義務化は、2024年から施行となる見込みです。
2021年4月に「相続登記を義務化する」改正法案が可決されたためです。
なお、義務化は24年以降ですが、それ以前の相続登記も対象となる見込みです。
つまり、2024年以降の相続登記についてのみ手続きをすればよいわけではなく、現在相続によって土地や不動産を受け継ぐ場合や未登記の土地や不動産も手続きが必要ということになります。
相続登記義務化で変化すること

相続登記の義務化によって変化することは、
・相続登記義務化、期限のある手続きとなる
・相続登記を放置するとペナルティがある
・相続人申告登記制度の新設
・登記手続きの簡略化
・土地の所有権放棄の制度化
です。各ポイントについて、詳しく解説します。
相続登記の期限が3年以内
相続登記が義務化されます。期限内に手続きを完了させなければなりません。
相続登記の期限は、相続の開始及び相続で不動産取得を知った日から「3年以内」です。
3年以内に不動産の相続登記(名義変更)をしなければなりません。
もしも、不動産を相続した事実を3年経過後に知った場合は、相続の事実を知った日から3年以内となります。
なお、2024年の施行前に相続を開始していた場合は、義務化となる施行日から3年以内に相続登記の手続きを済ませなければなりません。
期限の3年を過ぎると過料
相続登記を期限である3年以内に完了させないと、過料を科される可能性があります。
具体的には「10万円以下の過料」が科される見込みです。
過料は罰金とは異なり犯罪ではありませんので前科はつきませんが、お金を支払わなければならない金銭的な行政罰です。
相続で不動産取得を知った日から3年以内に相続登記(名義変更)をしないと、10万円以下の過料の対象となりますので注意してください。
相続人申告登記制度が新設
今回の法改正では、”相続人申告登記制度”が新設されます。
相続人申告登記制度とは、相続の申請しなけばならない人が「私が不動産の相続人です!」と申し出て登記をすることです。法務局の登記官に対して申告をします。
この制度は、相続で不動産取得を知った日から3年以内に登記ができない事情がある場合に適応されます。
相続人申告登記の具体的な申請方法について詳細は未定です。
相続人が単独で申請できて添付資料も簡易なものとなる見込みです。
すぐに相続登記ができない事情があるのであれば、期限前に申告をしましょう。
相続人申告登記制度を活用すべきケース
相続人申告登記制度は、主に遺産協議分割となったケースでの適用が想定されます。
相続登記の期限3年以内に、遺産協議分割が終わらないという場合です。
期限内に協議が終わらない見通しであれば、事前に相続人申告登記制度を利用することで、相続登記の義務を履行したものとして認められます。
ただし、この時点では正式な相続登記ではありません。
その後、相続人が確定したら、確定したその日から3年以内に正式な相続登記(名義変更)をする必要があります。
登記手続きの簡略化
相続登記の義務化に伴い、”名義変更手続き(登記)”が簡略化されます。
現状、相続人全員の了承を得て名義変更手続きを行う必要があります。
このまま相続登記義務化となった場合、非協力的な相続人がいると相続登記を行うことが難しくなります。
これを踏まえ、名義変更(登記)を簡略化し、スムーズに手続きを行えるようになりました。
遺贈のケースと、法定相続分での遺産分割のケースで名義変更(登記)が簡略化されます。
被相続人(故人)が相続財産を遺贈する内容を残していたケースでは、遺贈を受ける者が単独で申請可能となりました。
法定相続分の相続登記後、遺産分割による名義変更登記が必要なケースでも、不動産の取得者単独で手続きができるようになりました。
土地の所有権放棄の制度化
未登記の不動産を減らし、土地の有効活用を促進するために、土地の所有権放棄が認められる見込みです。
この制度により、土地を相続した場合、その所有権を放棄して土地を国庫へ帰属させることが可能になります。
相続した土地の中には、利用方法がない土地や売却が難しい土地が含まれることもあります。
そんな土地を相続した場合、これまでは所有権を放棄できず、固定資産税等を払い続けなければいけませんでした。
相続放棄という制度がありますが、土地の相続権だけを放棄することはできません。
法改正によって、不要な土地だけの相続放棄(所有権放棄)が認められれば、相続時に土地の所有権だけを放棄して、他の遺産は相続することが可能となります。
相続登記を放置するデメリット

相続放棄を放置し、3年の期限内に手続きをしなかった場合、どのようなデメリットがあるのか解説します。
不動産を売却できない
相続登記を放置するデメリット1つ目は、「不動産の売却ができない」ことです。
不動産を購入することを想像してください。
所有者のわからない未登記の土地を安心して購入することができるでしょうか。
相続登記や住所変更が放置されおり、登記簿で売主の名義が確認できなければ、不動産の購入希望者は不信感を抱きます。
そのため、未登記の不動産は売却ができないのです。
また、未登記の不動産を担保にローンを組むこともできません。
相続人が増えて将来の相続登記が困難になる
相続登記を放置するデメリット2つ目は、「将来の相続登記が困難になる」ことです。
相続登記を放置すると、世代を跨ぐほど、相続人がどんどん増加していきますよね。
相続登記の際には、現在名義人(故人)となっている方の相続人全員を探し出さなければなりません。
名義人の相続人を探し出すには名義人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。
もし相続人が死亡していれば、その相続人の出生から死亡までの戸籍謄本も取得しなければなりません。長期間にわたって相続登記が放置されていた場合、相続人を十数人も調べなければならないケースもあるのです。
実質的な所有者(名義人の相続人)を探し出したとしても、相続のためには、次にこれらの相続人の全員と交渉して同意を得る必要があり、非常に複雑な手続きとなります。
不動産の権利を失うことがある
相続登記を放置するデメリット3つ目は、「不動産の権利を失う」可能性があることです。
兄と弟の2人兄弟で、父親の不動産を分割するケースで解説します。
2人で話し合って「遺産分割協議し、父から相続した不動産は兄が取得する」と決着したとしても、兄が相続登記を放置してしまうと、登記簿上で兄が単独で相続したかどうかわかりません。
この場合、例えば、弟が第三者であるAさんに対象不動産の持分を売ってしまうことも可能です。
弟からAさんへの売却され、登記されてしまった場合、兄は遺産分割協議によって不動産を単独で所有していると主張することができません(民法177条)。
このようなケースを二重譲渡といいます。
判例上、最初に登記をした人が不動産の権利を取得することができるのです。
単独で不動産を相続することになった場合、早期に相続登記しないと、相続持分を売買されて登記されると権利を主張できなくる可能性があるので注意が必要です。
正しく相続できない可能性がある
相続登記を放置するデメリット4つ目は、「正しく相続できない」ことがあることです。
長期に渡り相続登記が放置されているケースでは、どのくらいの持ち分なのかを不動産登記簿によって確認することができません。
被相続人の相続登記がなされていない物件の共有持ち分を保有していたとしてもです。
そもそも認識を誤っており、持分を保有していない可能性もあります。
遺言書があったとしても、相続対象となる財産を正しく指定できないこともあります。
遺言の内容の一部が無効になってしまうどころか、遺言全体が無効になってしまうケースもあるのです。
相続登記を3年間放置してしまった事例
当事務所では相続登記を3年間も放置してしまった方よりご依頼を受けました。
ご状況としては、旦那様を3年前に亡くされた際に、旦那様と前妻の間のお子さん(相続人)に対して「相続登記に協力してほしい」と言い出せず、結果的に放置しておられました。
依頼者も体が弱くなってきており、このまま放置しておくわけにはいかないと、相続登記を行おうと思い立ったのですが、前妻やその子の所在が掴めなかったため当事務所にご相談にいらっしゃいました。
相続登記に必要な書類一覧
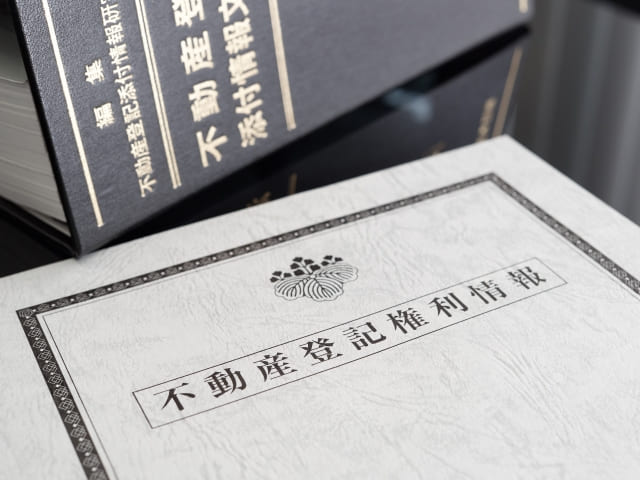
相続登記の手続きには、以下のような書類をご準備いただく必要があります。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・改製原戸籍・除籍謄本
・住民票の除票の写しまたは、戸籍の附票の除票
・法定相続人全員の戸籍謄本
・遺産分割協議書
・法定相続人全員の印鑑証明書
・相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写し
・相続する不動産の固定資産評価証明書
事情によっては、上記の書類以外に書類が必要な場合があります。
相続登記に必要な書類は法務局や市役所に受け取りにいきますから、すべて集めるのはかなり大変です。
相続登記を専門家に依頼するメリット
相続登記を専門家に依頼することで、期限のある相続登記の手続きをスピーディーにを完了させることができます。
相続人に代わって必要書類の収集~作成まで依頼可能です。
仕事の都合で、日中に市役所や法務局へいけない人は専門家に依頼することをおすすめします。
また、相続に関する知識が豊富ですから、難しいケースにも対応ができます。
例えば、相続人が多いケースなどです。
自分で手続きをすることが難しい場合や時間がない方や何代にも渡って相続登記をしてない場合は、相続登記の専門家である司法書士に依頼することをおすすめします。
当事務所では相続登記の無料相談を行っています
相続登記や遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧に対応いたします。まずは無料相談から。
予約受付専用ダイヤルは049-299-7960になります。
お気軽にご相談くださいませ。
相続登記サポートの内容・料金
当事務所の相続登記は3つのプランをご用意しております。
| 項目 |
相続登記 申請プラン |
相続登記 お任せプラン |
相続登記 まるごとプラン |
|---|---|---|---|
| 初回のご相談(90分) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 | × | 〇 | 〇 |
| 相続人全員分の戸籍収集 ※1 | × | 〇 | 〇 |
| 収集した戸籍のチェック業務 ※2 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 相続関係説明図(家系図)作成 | × | 〇 | 〇 |
| 残高証明書取得(預貯金・株式) | × | × | 〇 |
| 評価証明書取得 | × | 〇 | 〇 |
| 遺産分割協議書作成(1通) ※7 | × | 〇 | 〇 |
| 相続登記(申請・回収含む) ※3、4、5、6 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 不動産登記事項証明書の取得 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 預貯金の名義変更※8 (預貯金の名義変更までまるごと依頼したい方は こちらをクリック>>) |
× | × | 〇 |
| パック特別料金 | 35,000円~ | 80,000円~ | 95,000円~ |
※1 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※2 戸籍に不足がある場合、1通につき2,000円を頂戴致します。
※3 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※4 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※5 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※6 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※7 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、20,000円~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※8 預金口座名義変更は1口座までの金額になります。以降1口座追加につき40,000円頂戴致します。
この記事の執筆者

- 中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
-
保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号) 経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録
- 相続土地国庫帰属制度とは?内容や注意点を司法書士が詳しく解説
- 相続手続きの代行はどこに?各専門家の業務内容や司法書士に依頼するメリットを解説
- 相続登記義務化のポイント!放置すると罰則があります
- 2020年度の相続に関する法改正のポイント
- 不動産の名義変更(相続登記)のポイントと注意点は?売却はいつ検討すべき?
- 不動産の名義変更(相続登記)の手続き
- 当事務所の相続不動産の名義変更(相続登記)手続きサービス
- 遺族年金の受給
- 株式の名義変更
- 預貯金の名義変更
- 【相続】埼玉縣信用金庫の相続手続き(預貯金の解約・払戻・名義変更)について
- 金融機関の手続きでは「相続手続依頼書」が必要!?記入例や預貯金の解約の流れを解説
- 【相続】青木信用金庫の相続手続き(預貯金の解約・払戻・名義変更)について
- 【相続】埼玉中央農業協同組合(JA埼玉中央)の相続手続き(預貯金の解約・払戻・名義変更)について
- 【相続】川口信用金庫の相続手続き(預貯金の解約・払戻・名義変更)について
- 【相続】西武信用金庫の相続手続き(預貯金の解約・払戻・名義変更)について
- 【相続】中央労働金庫の相続手続き(預貯金の解約・払戻・名義変更)について
- 【相続】いるま野農業協同組合(JAいるま野)の相続手続き(預貯金の解約・払戻・名義変更)について
- 【相続】東和銀行の相続手続き(預貯金の解約・払戻・名義変更)について
- 【相続】飯能信用金庫の相続手続き(預貯金の解約・払戻・名義変更)について
- 【相続】埼玉りそな銀行の相続手続き(預貯金の解約・払戻・名義変更)について
- 【相続】武蔵野銀行の相続手続き(預貯金の解約・払戻・名義変更)について
- 生命保険金の請求
坂戸・東松山・鶴ヶ島で無料相談受付中!
- 初回相談無料!
- LINEで
予約可能! - 相続の
専門家が対応! - 無料相談はこちら
主な相続手続きのメニュー
相続のご相談は当相談窓口にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧
坂戸・鶴ヶ島・東松山で
相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで