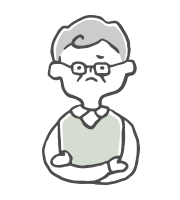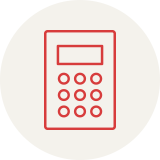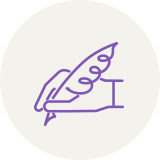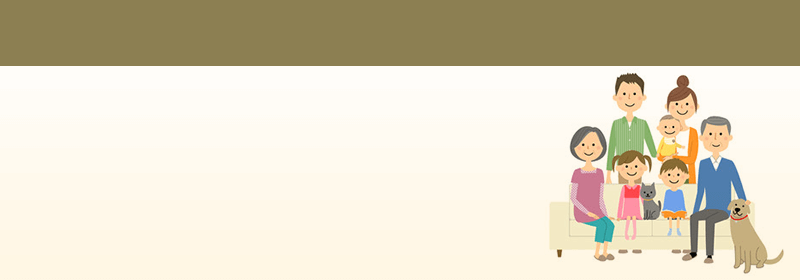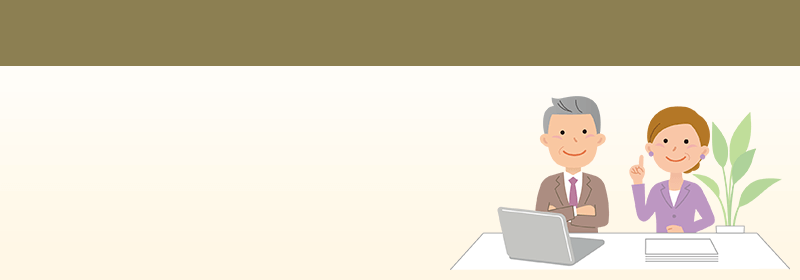課税対象財産
相続税の対象となる財産は大きく以下の3つに分類されます。
1.本来の相続財産
2.生前の贈与財産
3.みなし相続財産
1.本来の相続財産
この場合の財産とは、亡くなられた方が相続開始時に所有していた現預金、債権、株式、有価証券、不動産、借地権、著作権など、金銭評価できるすべての財産を言います。
反対に、金銭評価できない財産(たとえば、お墓や仏壇等)は、相続財産には含まれません。
※この意味で、生前にお墓を購入(墓石と墓地の永代使用権を購入)しておけば、相続税の節税の効果があります。
例えば、200万円でお墓を購入すると、現預金が200万円減少するので、その分の相続税がかからないことになります。他方で、お墓は「相続財産」とはみなされないので、「200万円のお墓を持っている」ということにはなりません。
結果として、相続財産が減ったことになるので、相続税を節税する効果があります。
なお、本人の死亡後に、遺族がお墓を購入しても、「死亡時における相続財産が減った」ということにはなりませんので、節税にはなりません。
2.生前の贈与財産
被相続人が生前に贈与した財産であっても、以下の場合には、相続税の課税対象になります。
(1)相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に、被相続人から贈与によって取得している場合、その贈与された財産の評価額が、相続財産に加算されます。
(2)被相続人から、生前に、相続時精算課税制度の適用を受けて財産を贈与されている場合、贈与された財産の評価額が、相続財産に加算されます。
これらの財産は、亡くなった時点では被相続人の財産ではなくなっていますが、相続税の計算上は、相続財産に加算して計算することになります。
3.みなし相続財産
本来的には被相続人の財産には含まれないけれど、相続税の計算上は相続財産とみなされる財産があります。これは「みなし相続財産」と呼ばれ、本来の相続財産に加算されることになります。
受取人の指定されている生命保険金や、死亡退職金などがこの「みなし相続財産」となります。
受取人の指定されている生命保険金は、民法上は「指定を受けている人の固有財産」と考えられており、本来の相続財産には含まれません。
しかし、この生命保険金も、被相続人の死亡を原因として発生しているものであるので、相続税の計算上は、相続財産として課税されることになります。
このような財産のことを、「みなし相続財産」と呼びます。
ただし、生命保険金や死亡退職金は、特別の控除を受けられる可能性があります。したがって、「生命保険金として受け取った金額の全てが、相続財産に加算される」というわけではありません。
この記事の執筆者

- 中島法務司法書士事務所 代表司法書士 中島 信匡
-
保有資格 司法書士(登録番号:埼玉 第1095号) 経歴 昭和55年 埼玉県坂戸市出身
平成 5年 坂戸市立千代田小学校卒業
平成15年 立教大学法学部法学科卒業
平成18年 司法書士試験合格
平成19年 行政書士試験合格(未登録)
平成19年 司法書士登録
坂戸・東松山・鶴ヶ島で無料相談受付中!
- 初回相談無料!
- LINEで
予約可能! - 相続の
専門家が対応! - 無料相談はこちら
主な相続手続きのメニュー
相続のご相談は当相談窓口にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧
坂戸・鶴ヶ島・東松山で
相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで