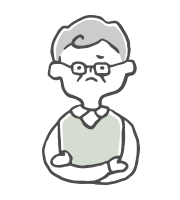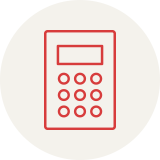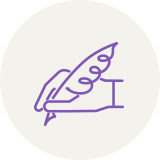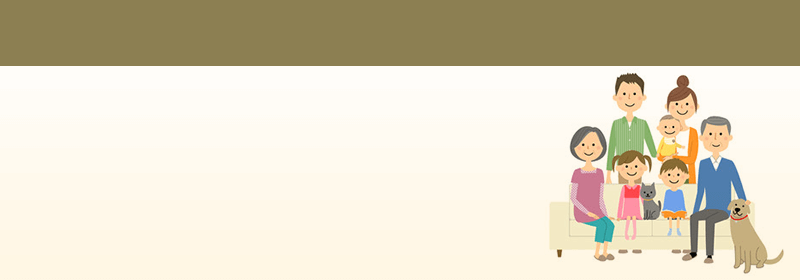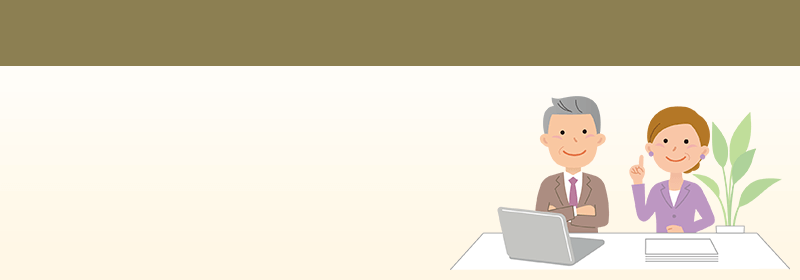自筆の遺言書で不動産の登記申請ができなかった事例
当事務所で解決した事例をご紹介します。
今回は、自筆で作成した遺言書の有効性の判断が、提出先によって変わってしまったケースです。
ご状況

ご相談者様のお父様は結婚を二回していました。
そこでお父様は、将来、子である相談者様と後妻の方との間で遺産のトラブルにならないように、自筆で遺言書を作成していました。
その内容は、不動産、預貯金その他財産のすべてをご相談者様に相続させるというものでした。
名前のみ(ファーストネームのみ)が書かれていて、名字は書かれていませんでした。
お父様が亡くなった後、ご相談者様はその相続手続に関して当事務所に依頼をされました。
当事務所のサポート

まず、家庭裁判所で遺言書の検認手続を済ませました。
次に、銀行で解約手続を行った際には、問題なく口座は解約され、ご相談者様に解約金が払い戻されました。
トラブルの発生
その後、不動産登記の申請をした際に、問題が起きました。
ご相談者様と遺言書に記載された「○○(相続人のファーストネーム)」が、人物を特定できているのかが問題となりました。
法務局の考え方としては、名のみ(ファーストネームのみ)で、名字の記載がない場合は、その相続人へ相続させるという趣旨なのか、同名の別人(親族ではない、第三者で、同名の人)に遺贈をしたものなかが、判断できないということでした。
当事務所と法務局との間で登記申請を認めていただくべく協議を行いましたが、結果として、登記申請は受け付けてもらえませんでした。
解決策
そのため、不動産の相続について相談者様と後妻の方との間で遺産分割協議を行わなければならなくなりました。
幸い後妻の方との間で無事協議が成立したため、遺産分割協議書を提出して不動産を相談者様名義に登記することができました。
遺言書作成のポイント

公正証書で遺言書を作成する場合には、フルネームや生年月日等を記載して、誰に相続させるか、人物を特定するのが一般的です。
今回の事例でもおそらく、ご相談者様の姓も記載されていれば不動産登記の申請も遺言書で行うことが可能だったと思われます。
今回は相続人の間で協議が成立したため、大きなトラブルとなりませんでしたが、もし後妻の方が協議内容に応じなければ遺言書のとおりに遺産をご相談者様が取得することは困難だったでしょう。
自筆での遺言は形式的な要件を満たせば一応効力が発生しますが、実際に相続手続で使用できない場合も起きえます。
自筆での遺言書作成は、第三者のチェックが入らないことが多いです。
このような意味でも、当事務所では、遺言書を作成する場合には、公正証書の遺言をお勧めしています。
公正証書の遺言であれば、問題が起きないかどうか、公証人からチェックしてもらうことができるからです。
相続・遺言の無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは049-299-7960になります。
お気軽にご相談ください。
遺言関連のサポート費用
|
遺言書作成サポート(自筆証書) |
50,000円~ |
|---|---|
|
遺言書作成サポート(公正証書) |
50,000円~ |
|
証人立会い |
10,000円/名 |
※公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。
坂戸・東松山・鶴ヶ島で無料相談受付中!
- 初回相談無料!
- LINEで
予約可能! - 相続の
専門家が対応! - 無料相談はこちら
主な相続手続きのメニュー
相続のご相談は当相談窓口にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧
坂戸・鶴ヶ島・東松山で
相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで